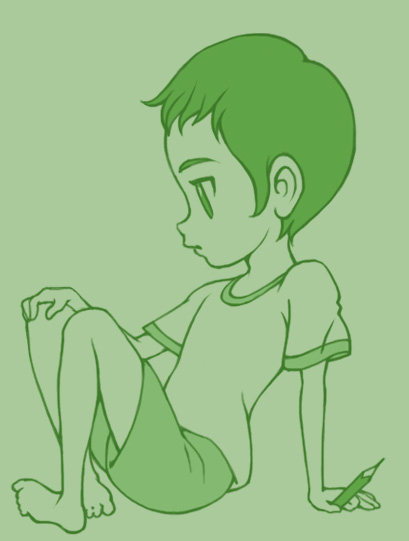No.10 太郎が居住地校交流に参加しない理由
特別支援学校に通う児童生徒は、『居住地校交流』という制度を利用することができます。
ところが、多くの人にとっては、居住地校交流って一体何やねん? というのが本音でしょう。
何を隠そう、僕自身もそうでした。
そんな謎多き制度である『居住地校交流』について、僕の個人的な考えをまとめてみようと思います。
まず、居住地校交流がどのような制度なのかについては、文科省のウェブサイトで以下のように説明してあります。
我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。
そのためには、障害のある人と障害のない人が互いに理解し合うことが不可欠であり、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、あるいは、地域社会の人たちとが、ふれ合い、共に活動する機会を設けることが大切です。
障害のある子どもが幼稚園、小学校、中学校、高等学校等の子どもと共に活動することは、双方の子どもたちの社会性や豊かな人間性を育成する上で、重要な役割を果たしており、地域や学校、子どもたちの実態に応じて、様々な工夫の下に進められてきています。
ふむふむ、なるほどねぇ。
つまり、特別支援学校の児童生徒が、自分の居住している地域の小学校・中学校に行って、近所の児童生徒と一緒に学習活動を行うことで、つながりを深めながら将来の生活をより豊かにしていくことを目的としているということでしょうか。
確かにこの部分だけを見れば、とても意義のある取り組みのように思えますね。
ところが、もしも手段が目的化されるようなことになっているのであれば本末転倒です。
そのあたりの現実がどうなっているのかについて、注意深く考察してみたいと思います。
ちなみに、居住地校交流を実施するための手続きとしては、『本人と保護者が交流の希望を支援学校に提出 → 支援学校が県教育委員会に申込 → 県教育委員会が市町村教育委員会に実施が可能か確認 → 可能な場合は支援学校へ決定通知を提出 → 支援学校と居住地校の担当教員が交流内容などを協議 → 居住地校交流の実施』という流れになっています。
「今日はなんとなく居住地校交流の気分だから、ちょっと近所の学校に行ってくるわ!」という軽いノリで実施できるわけではなく(そりゃそうですよね…)、それなりに杓子定規な制度としての面倒な手続きが存在しているわけです。
この面倒な手続きの存在によって、学校同士が気を使い合うことは容易に想像できるわけで、何らかの理由により、わざと交流の実施を難しくしているのではないかと思ってしまうのは僕だけでしょうか。
それでも居住地校交流を希望する子ども(または親)は毎回いますし、実施後のアンケート結果を見ても、『参加してよかった』という声が多数あることからも、関係者が満足できるような制度として運用されていることに関しては喜ばしく思います。
ただ、本来の目的である共生社会の実現に向けた取り組みになっているのかは微妙なところで、学年が上がるごとに希望者が激減しているという現状からも、さまざまな問題点はあるように思います。
では、太郎の場合はどうしているかと言うと、以前のコラム『中学校の特別支援学級ってどんな感じ?』でも書いたように、特別支援関連の交流イベントには積極的に参加しているのですが、実は居住地校交流には意地でも参加しないことにしています。
なぜなら、現在の居住地校交流の考え方が、分離教育制度を前提としたものであり、それを推進すればするほど、結果的に共生社会の実現をさらに難しくしていくからです。
特別支援関連の交流イベントの場合は、特定のラベリングをされた子どもだけが参加対象になっているという前提条件はあるものの、そのイベント内においては無用なラベリングなど存在せず、対等で健全な関係性が実現されています(もちろんこの場をインクルージョンな環境などとは言えませんが)。
一方、居住地校交流に関しては、明らかに障害児をお客様として迎え入れるために、受け入れる側が事前準備をバッチリ施し、障害のある児童生徒に楽しい思い出を作って帰っていただくために、完璧なシナリオに沿って執り行なわれる超絶面倒なイベントになってしまっています。
しかも、双方が『障害』と『健常』の役割を意識せずにはいられない(またはその部分にこそ学習の目的を見出している)イベントとなってしまっている側面もあります。
そのような堅苦しくて異質な環境の中に、「どーもどーも!」とか言いながら突入して行く勇気は僕にも太郎にも無いし、そのような分け隔てが有る教育環境というものには全く興味がありません。
そのくせどうして太郎が特別支援学校に在籍しているのかというツッコミに関しては、以前のコラム『インクルーシブ教育 vs 特別支援教育』を読んでいただければスッキリ解決するはずです。
現在の居住地校交流のやり方では、『障害児』と『健常児』が本当の意味でわかりあえること、つまり友達になることはできません。
障害児が、同級生からの心無い言葉によって傷ついたりすることがあるかもしれないけど、同時に楽しさやうれしさも共有しながら、クラスの仲間として多くの時間を共に過ごし成長できる環境こそが、居住地校交流に求められる意義だと思うんですけどねぇ…
昔の話になりますが、1970年代頃から取り組みが開始された制度化以前の居住地校交流は、今よりも理想的なかたちで(地域によって差はあれど)実施されていたようです。
というのも、養護学校に通う児童生徒が、居住地校の通常学級で行なわれる日常的な授業に頻繁に参加できていたからです。
例えば、毎週のように授業に参加して一緒に給食も食べたり、体育祭や修学旅行や宿泊学習にも自然なかたちで参加できていたそうです。
これこれ、これこそが本来の居住地校交流ですよね。
ところがどうでしょう、現在の居住地校交流(こちらも地域差はあれど)は、1年に1~2回しか開催されないような超激レアなプレミアムイベントに成り果ててしまい、保護者まで同席のもと、特別支援学校の児童生徒が特別なお客様として、入念に準備された環境の中に拍手で迎えられるという、日本アカデミー賞もビックリの一大イベントと化しています。
完全に手段が目的化してしまっているというやつですね。
これって、東西南北どこから見てもインクルージョンな環境とは言えません。
そのような現状であるにもかかわらず、文科省や教育委員会が、インクルーシブ教育を推進するために居住地校交流に力を入れていると宣言しているあたりは、なんとも言えないシュールな笑いを誘います。
実際に、国連子ども権利条約委員会から、再三にわたって分離教育を改めるよう勧告を受けているにもかかわらず、その回答が『交流及び共同学習によって、統合教育が進展している』ですからね。
しかも、おそらく超真剣な眼差しと渾身の演技力でこのセリフを発言しているあたり、じわじわ来るものがあります。
もちろん、そのようなかたちの居住地校交流を望んでいる人もいるだろうし、それこそが共生社会を目指すための交流のあるべき姿だと勘違いしている人もいるはずなので、現在の取り組み自体を否定はしませんが、僕にとっては全く興味の無い世界の話というだけです。
僕がインクルーシブ教育を推進して、その実現を目指す側の立場である以上、現在の居住地校交流に参加しないことは当然の選択です。
では、太郎が地域の同級生と全く関わりが無いかといえば、そんなことはありません。
例えば、太郎と一緒に車で近所を走っていると、保育園時代の同級生が「太郎く~ん!」と叫びながら車を追いかけてきます。
車を停めて窓を開けると笑顔で挨拶をしてくれるのですが、その全力ダッシュと心からの笑顔が、友達への思いを自然に表現した行動だと思うと、うれしくて仕方がないのです。
例えば、太郎と一緒に土曜日に居住地校のグラウンドで遊んでいると、学童保育を利用している保育園時代の同級生がダッシュで集まってきて、太郎の手を引っ張ってどこかに遊びに行きます。
これもまた、友達と一緒に遊びたいというだけの自然な思いから表現される行動であり、その姿を眺めているだけで、うれしくて仕方がないのです。
例えば、平日の放課後に居住地校のグラウンドに遊びに行った際は、教室の中から同級生が何人も飛び出してきて、太郎の周りに集まってきてくれます。
ところが、その時はまだ掃除の時間だったらしく(支援学校の下校時間が少し早かったようです)、子ども達は先生に怒られながら教室に連れ戻されていきました…
平日の放課後は下校時間の違いに気をつけないといけないなぁと反省しながらも、子ども達の中から湧き出てくる、友達としての自然な行動を見せられると、うれしくて仕方がないのです。
例えば、太郎と一緒に近所の公園で遊んでいると、保育園時代の同級生がやってきて「太郎くん、よくしゃべるようになったね。保育園の時はあまりしゃべらなかったのに。」と言ってくれます。
そのような言葉を聞くと、あの子には自閉症という障害があって… とかいう発想そのものが、大人による一方的なラベリングにすぎないということがよくわかります。
子ども達にとっては、障害とか健常とかはどうでもよくて、あの子はよくしゃべる友達とか、あの子はあまりしゃべらない友達とか、単なる個性としてしか見ていないんだなぁと思うと、うれしくて仕方がないのです。
そういうわけで、保育園時代の同級生と会うたびに、本当のインクルージョンな環境というものがどういうもので、その環境によって築かれる本当の友達関係がどういうもので、その友達関係によって達成される共生社会の姿がどういうものなのかを、実感せずにはいられません。
学校によって強制的に作られた環境の中に迎えられる『お客様』になるつもりは毛頭無く、『友達』として一緒に遊んでいるだけのその環境こそが、太郎にとっての日常であり、僕が望む自然な環境でもあります。
もちろん高学年になってくると、今と同じような状況が続く可能性は少なくなるかもしれませんが、そのような意識の変化を誘発しているものこそ、現在の居住地校交流や分離教育制度などによって作り出される『障害』と『健常』を分ける価値観のように思えてならないのです。
大人達によって、「障害者とはこういう存在であり、君達は障害者に対してこのように接しなければなりません。」などと教科書的な指導をされるたびに、子ども達の中にある『友達』が『お客様』に変化していくのであれば、それは残念なことであり、結果的に共生社会の実現さえも遠のいていくでしょう。
だからこそ、学校主体で実施されるような居住地校交流ではなく、楽しいことも嫌なことも共有できる『友達』として、子ども主体で一緒に遊べる日常を、これからもできる限り大切にしていきたいのです。